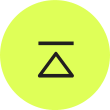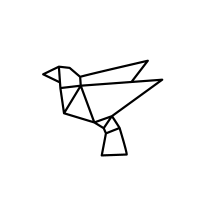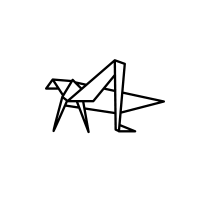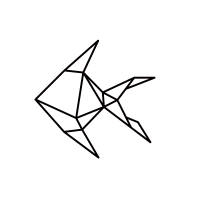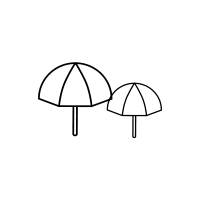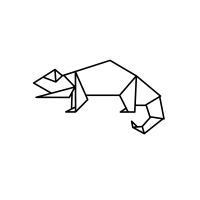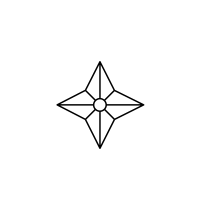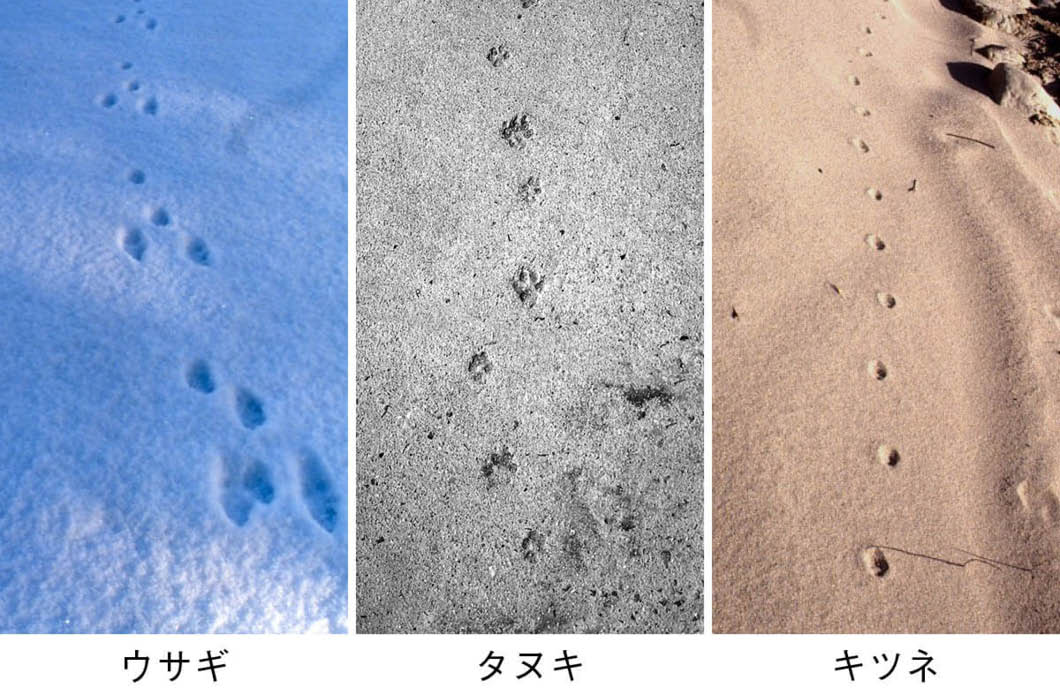ゆったりとしているようで逞しいカワウの魅力と生態
カワウの雄と雌は体の大きさに違いがあり、我々人間と同様、雄のほうががっちりしていて体重も重い(雄の体重が約2000〜2500g、雌の体重が1500〜2000g)。特に嘴は雄の方が長い傾向にある。「傾向にある」というのは、中には雌より小柄な雄がいるし、その逆もいるからだ。たぶん、この写真の子は雌。しかも、若い。後頭部から胴にかけてのラインがしなやかで、目がやさしい。この鳥の魅力的な生態の一端を紹介しよう。

カワウ。この写真の個体は嘴の長さと羽色からして、若い雌だと推測する。【Photo by 渡辺美郎】
ゆったりと生きているように見えるカワウ
野生動物は、捕食者から自身の身や我が子を守らなければならないし、食べ物を手に入れ続けなければ飢えて死んでしまう。このように厳しい生態系のルールの中では、ゆったりと構えている暇はないはずなのだが、カワウはどこかゆったりと生きている。
ゆったりとしたその生き方を垣間見たのは、10年以上前のこと。東京湾でカワウの終日行動を追跡していたときだ。陽が徐々に傾き、夕暮れに向けて、海からねぐらに帰るカワウが増えてきていた。私は、海の真ん中にある杭の上にとまっているカワウがいつになったら飛び立ち、ねぐらに戻るものかと、他のカワウの動向にも目を走らせながら、待っていた。
ところが、いつになっても飛び立たない。もうすでに杭は水面下に没し、脚の半ばまで水に浸かっていた。ちょうど、東京湾は潮が満ちてきているところだった。若いカラスなら脚が濡れるようになった変化に気づいて驚き、ことによっては、はしゃいで飛び上がったり、着水したりを繰り返したに違いない。
しかし、どうしたことだろうか。目の前のカワウは、脚が完全に水中に隠れ、腹が濡れ、胸まで潮が満ちてきても、姿勢を変えることなくそのまま立っている。そして、数刻ののち、その体が揺れ始めた。体が水面に浮いてしまったのだ。
双眼鏡越しのシルエットには、その間、動じた様子もなく、変化をそのまま受け入れているようだった。潮に流されて少しずつ、少しずつ、もと居た場所を離れていったのが印象的だった。

真夏の夜明けの東京湾。河鵜(カワウ)という名前だが、河口や沿岸部の方が彼らの食べものは多い。
コロニーで採食場所の情報収集?
とある河川でカワウの飛翔方向を調査していた時のことだ。確か、上流からだったと思うが1羽のカワウが飛来した。頭上を通過して少し過ぎたころ、下流から別の1羽がやって来てすれ違った。すると、上流から下流を一目散に目指していたはずのさきほどのカワウがきびすを返し、下流から来た1羽を追って、もと来た方角へ飛んでいくのだ。「なんと、主体性のない……」と、再び頭上を通過するカワウを眺めながら、心の中で呟いてしまったのを覚えている。
生態学の用語には、「情報センター仮説」なるものがある。これは、主に鳥のコロニー(集団繁殖地)が進化した理由を説明するための仮説だ。カワウのコロニーのように多数の個体が集まる場所があると、そこは良質な採食場所などの情報交換の場として機能し、ばらばらに繁殖するよりも進化的に有利だ、だからコロニーを形成するように進化したのだ、という仮説だ。
この場合、情報は、たとえば一目散にコロニーを飛び立って採食場所に向かう行動や、たくさん食べることができた結果として現れる健康状態の良さなど、ある個体が他個体を見て読み取ることで取り交わされる(人間のように会話がなくても、他個体から情報を得ることは可能なのだ)。
コロニーの進化にこの仮説が機能していたかどうかはともかく、コロニーが情報センターとして機能している可能性は十分考えられる。私に「主体性がない」と断罪されたあのカワウは、もしかすると、すれ違った個体から一瞬にして良い採食場所のにおいを感じとった、鋭い感覚の持ち主だったのかもしれない。
川の水が澄んでいれば、上空を飛ぶカワウからすれば、魚の群れの位置は一目瞭然だ。上空を飛ぶカワウを見ていると、時折首をひねって頭を横にしていることがある。片目を水面に向けて水の中を除き込んでいるのだ。一羽が魚の群れを見つければ、翌日には、何羽か仲間がくっついてやってくる。ねぐらとの距離にもよるが、カワウが群れを成してやってくるのに、そう長い時間はかからない。

羽ばたきと滑空をうまく使い飛ぶ、その速さは時速50kmを超える。【Photo by 渡辺美郎】
迫力溢れる採食行動
主体性のなさは、見方を変えれば、協調性の高さとも取れる。群れて行動する鳥は、群れでいることによるメリットを享受するため、余計な争いを生まない性質を進化させてきている。
カワウが群れで魚群を追うところを目撃したことはあるだろうか? カワウ同士が採食なわばりをかまえて対立したり、一つの魚を奪い合ったりすることはなく、群れは、一糸乱れぬ統制のとれた動きで行動する(実際には各々がよりたくさんの魚を得るために行動しており、統制などというものは恐らく存在しないが)。群れの後ろにいるカワウは、前のカワウの上を飛んで追い越して最前列に着水し、潜水して魚を捕らえる。次に一番後ろになってしまったカワウは、また前にいるカワウを追い越して着水、潜水して魚を捕らえる。
その光景には、追うカワウと追われる魚の命をかけた戦いの迫力がある。きっと、あのゆったりとしたカワウもスイッチが入って頭をフル回転させているに違いない。水面に出した顔には気迫のカケラもないが、間髪入れずに潜りなおす行動は、杭の上にいるときとはまるで様子が違う。
水中の戦いはスピード勝負だ。カワウの4本の趾(あしゆび)の間には、3枚の水掻きがあり、この脚を両脚そろえて後ろに蹴りだすキックは強力だ。海外のやや大柄な別亜種のカワウの研究では秒速最大4mにも達するとされ、川魚の中では泳ぎが速いと言われるアユの秒速約2mですら余裕で捉えるのだから、障害物がない河川で軍配がカワウに上がるのは自然なことだ。日の出から採食を始めたカワウは、私たちが朝出勤する時間には、あらかた1日分の食事を済ませてしまっている。採食に多くの時間を割かなくて良い余裕が、彼らの思考をゆったりさせているのかもしれない。

東京湾の埋め立て地の間で採食する約70羽のカワウの群れ。飛んで移動しているカワウと顔をあげている個体以外は、水中で魚を追っている。

ほぼすべてのカワウが姿を現したところ。
逆境を生き抜く生命力あふれるカワウ
どこかのんびりしているように見えて、しっかりまわりを観察して判断し、やるときはやるカワウ。今回は紹介しなかったが、外敵を正しく恐れて危険を回避する力や、小さな雛たちを暑さや寒さから守る親鳥の愛情も持っている。たくさんの仲間が撃ち落とされても、したたかに生きているのだ。どんな生きものでも、絶滅せずに今まで子孫を繋いできているからには、進化の中で勝ち得てきた魅力をたくさん、その内に秘めているのだ。

2羽のカワウの雛と親

翼を乾かす繁殖羽の成鳥。カワウの羽は潜水しやすくするため、水を弾かない。【Photo by 渡辺美郎】
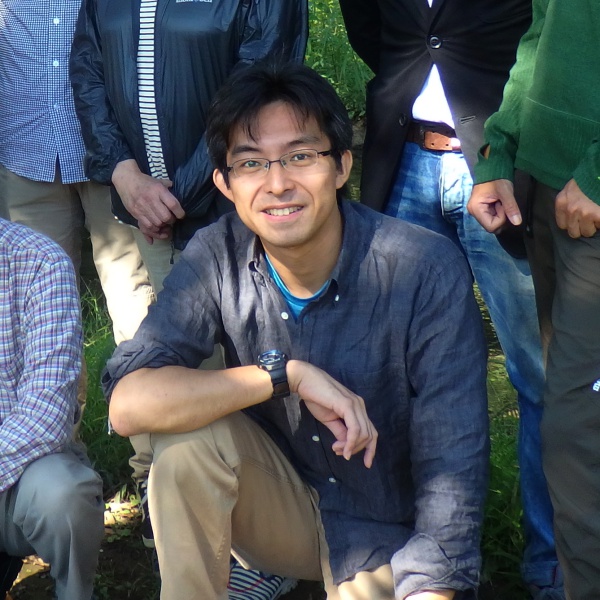
Author Profile
高木 憲太郎
NPO法人バードリサーチ研究員。大学院でカラスを研究していたせいか、就職した野鳥の会でカワウの担当に割り振られて以降、カワウとは16年の付き合いになる。カワウの業務のほか、全国の会員と共に鳥の生息状況の調査(最近はホシガラス)なども行なっている。
参加型分布調査プロジェクト「ホシガラスを探せ!!」
http://www.bird-research.jp/1_katsudo/hoshigarasu/hoshiQ2.html