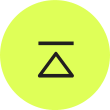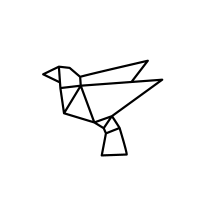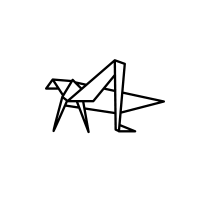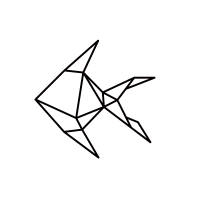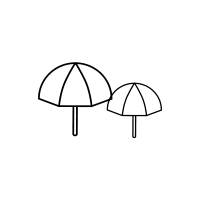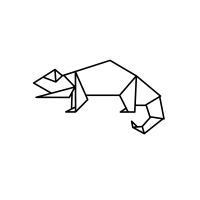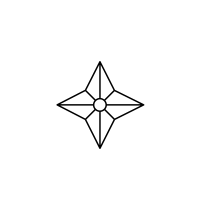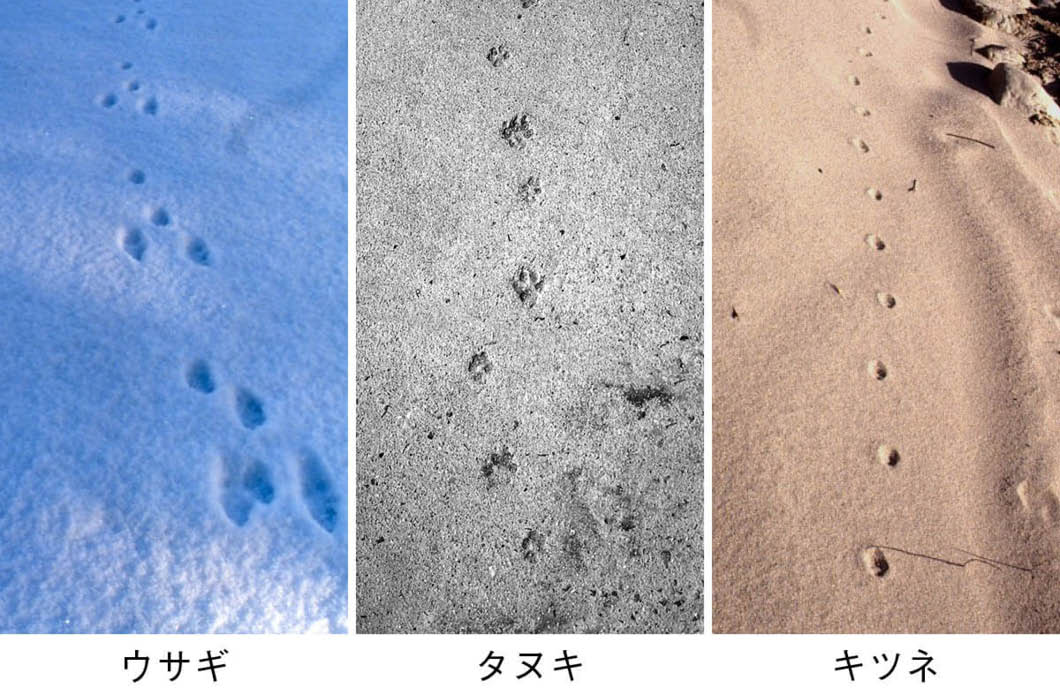きのこは本当に秋に生えるのか?
データをもとに発生のピーク時期を検証
秋も深まってきた今日この頃ですが、きのこ好きの皆様を中心に、「秋といったらきのこ!」というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
さすがにそこまではいかなくとも、「きのこの季節といえば?」という質問にはほとんどの方が「秋」と答えることと思われます。
しかし、本当にそのイメージは正しいのでしょうか?当たり前だと思っていることでも、データを収集して調べてみることで、意外な発見があるかもしれません。
本記事では「GBIF(Global Biodiversity Information Facility:地球規模生物多様性情報機構)」という世界中の生物多様性データを集積したプロジェクトのデータベースを解析することで「きのこは本当に秋に生えるのか」という疑問を検証してみました。

世界各地の情報はGBIFポータル(http://www.gbif.org/)から確認できる
10月がきのこの最盛期
それでは、早速GBIFで解析したデータを見ていきましょう。
その前にまず、「きのこ」のほぼ全てが「担子菌(たんしきん)」および「子嚢菌(しのうきん)」というグループに含まれますが、2018年9月の時点で、GBIFには担子菌と子嚢菌合わせて151,764種が登録されていました。

子嚢菌と担子菌の違い
この中から日本国内で採集あるいは観察され、かつ発生月の情報を含むデータが存在する種を絞り込むと、計5,853種(データ84,835件)でした。ただし、この中にはデータの乏しい種もあり、「きのこ」の他にカビや地衣類なども含まれているので、もう少し絞り込む必要があります。
種ごとの曲線を描くのに必要なデータ数を確保するため、国内データが50件以上存在する種に絞り込むと435種となり、そこから手作業で「きのこ」以外を除くと268種(データ25,160件)が残りました。
種ごとに最もデータの多い月を算出し、月ごとの頻度の割合をグラフで表したのが下図です。

「担子菌きのこ」「子嚢菌きのこ」のいずれも、10月がピークの種が最多であることが分かります。「やはりきのこは秋のもの」と言っても、全体の傾向としては間違いではないようです。
年間を通してきのこを観察している筆者の経験から考えても、この結果は妥当だと思います。ただし、全てのきのこがそれに当てはまるわけではなく、冬がピークの種はほとんどありませんが、春や夏がピークという種も少なからず存在しました。
食用きのこは秋に生える
次に、種ごとの発生の推移を見てみます。
主な種をピックアップしてヒートマップで図示し、ざっくりとパターンを分類してみました。

ヒートマップの縦軸はきのこの種、横軸は発生月を表す。緑色が濃い月ほど発生量が多いことを示している
まず、一番上のテングタケ、イグチ、ベニタケは一般的に「夏」のきのことして認識されているグループですが、8月に一旦発生量が減り、再び秋に発生量が増加する傾向が見られます。
つまり、ピークが2つある「二峰性」の発生パターンを示しています。

テングタケ科の代表種タマゴタケ(写真提供/BuNa編集部)

イグチ科のヤマドリタケモドキ(写真提供/BuNa編集部)
次に、10月に単一のピークがあるのが「秋」のきのこからなるグループです。
この図では多くの種を省略していますが、このグループが種数、多様性ともに最大となりました。近縁な種は概ね発生傾向も類似していますが、チチタケ属のように、種レベルで異なる場合もありました。

秋の定番ハナイグチ(ヌメリイグチ属)。地方により「ジゴボウ」や「ラクヨウ」とも呼ばれ秋にカラマツ林から発生する(写真提供/BuNa編集部)

チチタケ属の一種。栃木県では「チタケ」という名で広く食用とされている(写真提供/BuNa編集部)
この他、サルノコシカケ類のように子実体の耐久性が高く「通年」見られるグループ(数年~数十年にわたって生長を続ける多年生の種もある)、アミガサタケやハルシメジのように「春」にピークがあるグループ、マツカサキノコ属やムラサキシメジのように「晩秋」にピークがあるグループ、などに分けることができそうです。

春を代表するきのこアミガサタケ。ヨーロッパでは「モリーユ」と呼ばれ季節の食材として珍重される(写真提供/BuNa編集部)
以上の結果をまとめると、きのこの発生時期はいくつかのパターンに分けられるものの、秋に発生する種が最も多く、これが一般的な「きのこ=秋」のイメージの形成に影響しているのではないかと思われます。
…しかし、本当にそれだけでしょうか?
もちろん、野山を歩いていて秋にきのこが多く見られるのも事実ではありますが、「世間一般におけるきのこのイメージ」はやはり「味覚」と強く結びついていると思われます。
もう一度、データに立ち返って考察し直してみましょう。 じつは、マツタケ、ハナイグチ、ナラタケ、コウタケ、ホンシメジ…など、きのこ狩りの対象になる食用きのこの多くが、今回の分類のうち「秋」グループに含まれました。
一方、「夏」のテングタケは広く知られている通り、ほとんどが毒きのこです。「夏」のイグチやベニタケには食用きのこもありますが、「夏限定」ではなく秋に再登場するものが多いので、夏のきのこという印象が薄いのではないかと思われます。
本当はきのこは春のもの⁉
さて、「(一般に馴染み深い)きのこは(例外もあるけど)確かに秋に生える」という結果が得られたので、これにて解決!としてもよいのですが、その「例外」にもさらに踏み込んでみます。
例えば、チャワンタケの仲間(盤菌類)を考えてみると、図に掲載した2種(アミガサタケ、ブナノシロヒナノチャワンタケ)の他にも、ツバキキンカクチャワンタケ、キボリア・アメンタケア、フクロシトネタケ、キツネノワンなど、比較的目立つ種がいずれも「春」のきのこであることから、このグループは「秋」ではなく「春」にピークがあるのでは?という印象がありましたが、今回の結果はその予想を裏付ける形になりました。

サクラが咲くよりも早く、ツバキの花が終わる早春に発生するツバキキンカクチャワンタケ(写真提供/BuNa編集部)
チャワンタケは子実体が微小であまり採集されない上、同定も難しいグループで、未知種もまだまだ存在すると思われます。
つまり、今回の解析では、自然界における発生を過小評価してしまっている可能性が高いのです。
仮に全てのチャワンタケの発生データを余すところなく収集できたとすると、全体として「きのこは春に生えるもの!?」という異なる結論が導き出される、かもしれません。
また、通年存在するように見えるサルノコシカケ類も、一年のどこかで子実体が生じているはずで、生長途中の柔らかい子実体が見られる時期があったり、採集しても胞子をつくっていない時期があったりすることからも、一定の季節的な消長(フェノロジー)が隠れていることは想像に難くありません。その発生時期が「秋」なのかどうかを調べた研究は、少なくとも筆者は目にしたことがありません。
発生予測は可能なのか?
きのこの多様性および生態を理解する上で、発生地と発生時期の情報を含むGBIFデータはとても有用で、今後さらなる拡充が期待されます。
しかし、より実用的な、例えば「年ごとのきのこの発生傾向(あるいは豊凶)」を予測したり一般化したりする目的では、利用可能なデータの量が不足しているのが現状です。
いわゆる「人工知能(AI)」の関連技術である「機械学習」によるアプローチが有望かもしれませんが、それにも桁違いに大量のデータが必要です。また、GBIFデータは発生した地点と日付の情報を含む一方、「何本生えたか」といった「発生量」のデータを通常含まないので、この種の検討には不向きかもしれません。
「天然きのこの発生予測」において、現在最も豊富にデータが蓄積されている種は間違いなくマツタケです。
長年研究対象とされてきたマツタケに関しては、地温が19°Cまで下がると子実体を形成し始める性質があること、年ごとのコロニー(シロ)の生長速度や分布の変化、気温や降水量などの要因が発生量に及ぼす影響など、様々な知見が得られています。しかし、その基となったデータはGBIFのように誰でもアクセスできる状態にはなく、ほとんどがいわば「お蔵入り」の状態です(ちなみにマツタケの国内GBIF観察データ数は44件で、50件に満たないことから今回の解析からは除外されました)。
また、きのこの発生パターンが複数あるという今回の結果から、マツタケの研究成果を他の種にそのまま当てはめることができないことも明白です。マツタケでは「豊凶指数」という指標が提案されていますが、秋に生えるきのこも、そうでないきのこも存在する中で、気象要因からきのこ一般の発生傾向を統一的に説明することは可能なのでしょうか?
それを実現するためには、様々な種の子実体発生データを集積し、オープンデータとしての公開に繋げるための、これまでにないシステムが必要ではないかと思います。
【補足】今回の解析には、前述のようにGBIFというデータベースを用いています。GBIFとは、世界中の生物多様性データを集積し、自由に使えるオープンデータとして公開しているプロジェクトです。博物館の標本データや生態学的研究のデータなど、菌類を含むあらゆる生物が「いつ」「どこで」観察されたかという情報が豊富に収載されています。PCが一台あれば、誰でもその膨大なデータの全てを解析対象とすることができます(※)。
※今回筆者はプログラミング言語のPythonと「pygbif」モジュールを使用して解析しましたが、プログラミングはちょっとハードルが高い…という方は、GBIFのWebサイトから検索結果をcsvファイルとしてダウンロードし、Excelなどの表計算ソフトで本記事と同様の集計を試してみることも無理ではないと思われます。ただし、プログラミングを使うことで様々な条件を複雑に組み合わせた検索が可能になり、大量のデータの取得や処理も自動化できるので、ぜひ挑戦してみることをおすすめします。

Author Profile
中島 淳志
1988年生まれ.アマチュア菌類愛好家(マイコフィル).学生時代の専攻は菌類分類学.普段は財団職員として医薬論文の情報検索や抄録作成などに従事.菌類学文献にも医薬分野と同じように体系的な索引付け(インデキシング)が必要との思いから,その日に読んだ論文の情報をデータベース(大菌輪)としてまとめている.