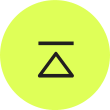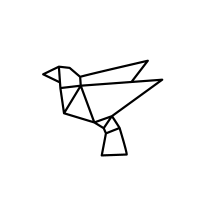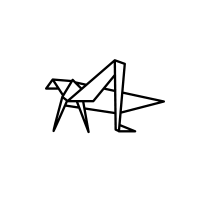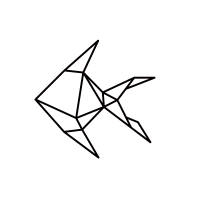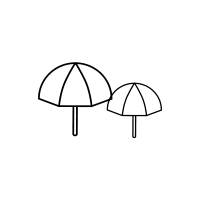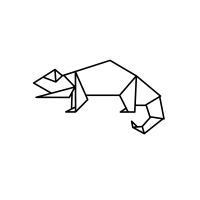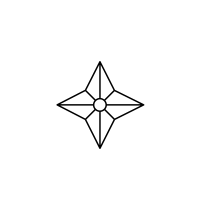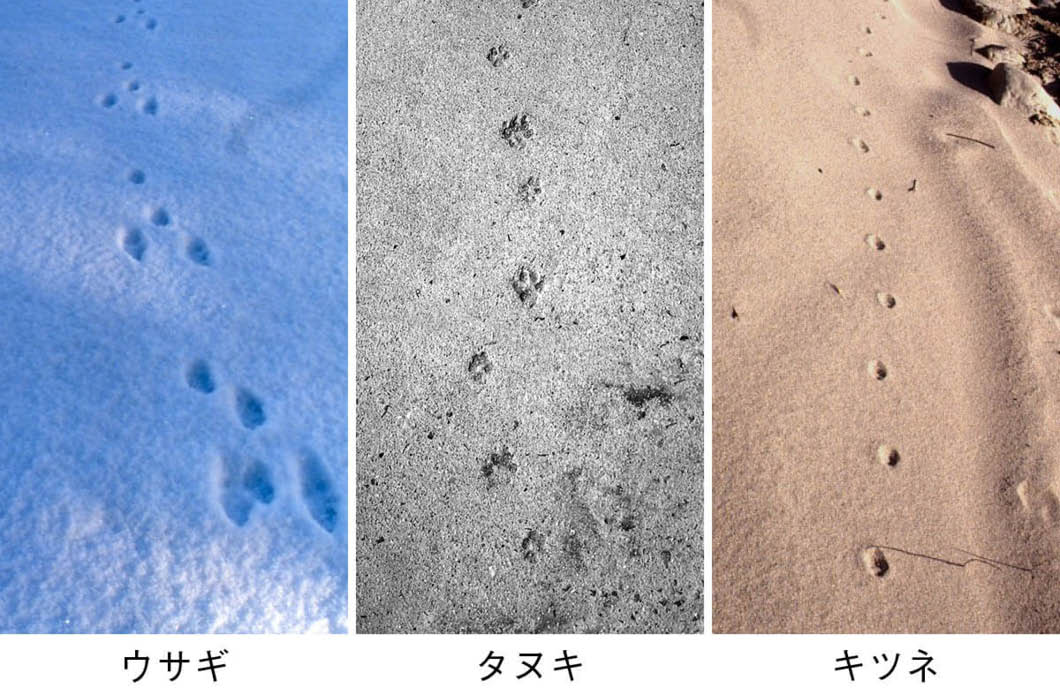なぜすしにはワサビが入っている? 〜わさびの日本史〜

ツーンとするけど、美味しさが増す香辛料のワサビ。それにしても、なぜすしにはワサビがつきものなのか? ワサビ研究者である山根京子さん(岐阜大学准教授)が、その理由を解説します。
(本記事は『わさびの日本史』(文一総合出版)から抜粋・一部変更して構成しています)
「すし(寿司)にワサビ」はもはや世間の常識といってもよいだろう。世界的にも有名な組み合わせといえるのではないだろうか。
しかしながら、ワサビやすしの個々の歴史と比較すると、組み合わせとしてはそれほど古くない。「刺身にワサビ」が定着するのは比較的新しい時代であり、「すしにワサビ」も、さまざまなすしの形態が存在していた頃にはワサビとは組み合わせられず、ワサビは「握りずし」と出会うことで定着するようになる。
江戸で生まれた「握りずし+ワサビ」の食文化
握りずしの文化を生んだのは江戸である。江戸の特徴は、渡辺善治郎の著書『巨大都市江戸が和食をつくった』が参考になる。そこから、まずは握りずしが生まれた時代の歴史的背景を見てみよう。
そもそも江戸は、徳川氏が江戸城に入城した天正十八年(1590年)に始まるといってよい。当時はごく小さな城であったが、慶長八年の徳川幕府の成立から本格的な都市づくりが始まり、その後百年ほどの間に人口百万人(半分は武士)を抱える巨大都市が形成されたのである。武士階級の経済基盤は年貢収入であった。そのため、農村部では米の大半が年貢として取り上げられ、自由に米が食べられなかったとされるが、都市では米中心の食事であり、全国で最も米を食する都市となっていた。白米が食されていたので、「江戸わずらい」とよばれるビタミンB欠乏による脚気が流行したのも有名な話である。
また、江戸は男性の比率が異常に高い都市でもあった。そのため外食文化が発展した。こうして江戸では、貨幣経済の発展にもともない、「宵越しの銭は持たない」というような消費傾向の強い、とくに食に関して強い社会が形成されたのである。なかには借金までして初物食いに熱中する食文化現象がみられた。
このような時代を背景に、江戸の四大名物食(蕎麦きり、てんぷら、うなぎ、握りずし)がうまれる。このうち、握りずしは最も歴史が新しい食べ物である。このなかで最も古いのは蕎麦切りであり「定勝寺(じょうしょうじ)文書」(1574年)が最も古い記録とされている。
蕎麦の薬味としてのワサビ利用に関しては、具体的な時期は不明であるが、1751年に江戸の蕎麦通日新舎友蕎子が書いた「蕎麦全書」に、大根の辛いものがないときの代用品として「山葵」を使うと書かれている。このことから、四代名物食のうち、最も早くワサビとの組み合わせが親しまれるようになったのは蕎麦と考えてよさそうだ。
さらに、あまり知られていないかもしれないが、東京湾の漁場面積当たりの生産額は、明治、大正、昭和を通じて日本一であったというデータがある。つまり、日本の江戸は世界一の漁場であったと言っても過言ではなく、こうしたことを背景に握りずしのブームの基盤となる環境が整ったといえるのである。
大正から昭和初期:料理人とともに地方に広がった握りずし
江戸時代、握りずしは「江戸の郷土料理」という位置づけであった。では、いつ頃全国へ広がったのだろう。急速に全国に広がったのは、大正から昭和初期にかけてとされている。関東大震災(1923年)で被災した料理人が東京をはなれ、地方に移り住み、江戸の食文化が一気に拡がったようだ。さらに、太平洋戦争でも東京を追われた職人も数知れず、握りずしの伝播につながったとされている。
「すし」は全国各地で特色のある料理法が存在していた。新しく登場した握りずしが日本中を席巻するに至った背景には、何があったのだろうか。
戦後の法令と握りずしの全国展開
実はある重要な法令が出されていた。1947年の「飲食営業緊急措置令」である。戦後の食糧難のもと、アメリカに食料援助を受ける状況で、外食産業が規制を受けたのである。当然すし屋も対象となるはずであった。ところが東京都のすし商の組合が交渉し、「一合の米と引き替えに加工賃を取り、十かんの握りずしを作る」ことで、すし屋は飲食業ではなく「委託加工業者」として営業の許可をとることができた。その結果、全国各県のすし屋がこの方式を取り入れたため、結果的に、握りずしでなければ正規の商売ができないという図式ができあがってしまった。これにより、握りずしの全国展開が決定的なものとなり、現在に至ったとされている。握りずしとワサビの組み合わせによりワサビの普及がすすんだことを考えると、ワサビの運命に大きな影響を与える出来事であった。
現代はワサビぬきが普通?
こうして握りずし文化は現代にも受け継がれることになった。ところが、「ワサビとすし」の最強と思われてきた組み合わせにも、近年変化の兆しが見えはじめている。1958年に日本で初めての回転寿司が大阪で誕生し、現在では回転ずしが「すし文化」の一翼を担いつつある。ところが今、回転すし店では、子供たちが多く利用することもあり、すしとワサビが切り離されるようになってきた。少し前までは、「さび入り」、「さび抜き」が皿で区別されるなどしていたが、現在ではほぼ全ての店舗で、最初からはワサビを加えない「さび抜き」が基本になってしまっている。スーパーのパック入りのすしにも、最初からワサビが入っているものはほとんど見られなくなってしまった。このままでは、何世代か後の日本で「すしにワサビ」が当たり前でなくなる日がくるのではないかと私は本気で危惧している。将来、本書が誰かの目にとまる日が来た時、すしとワサビの関係がどのような状況で読まれるのか、少々おそろしい気もする。
ワサビの特徴 〜栽培が難しく、生育期間が長く、大量生産に向いていない!?〜
「握りずしにワサビ」、「刺身にワサビ」の文化が江戸後期から定着しつつあったといっても、現在のように、日本全国津々浦々まで浸透するためには、ワサビは特殊な植物でありすぎた。一番の問題は、一般的な野菜と比べて栽培が難しく、生育期間が長いため、大量生産に向いていない点である。

また、もともと水分の多い環境で育つ植物であるため、常温、乾燥状態では鮮度が落ちやすい点もあげられる。
さらに、ワサビの辛味は揮発性で、時間がたつと抜けてしまうのも難点といえる。そもそも、ワサビの辛味の本体は「アリルイソチオシアネート(AITC)」とよばれる成分で、カラシやダイコンなど、他のアブラナ科植物にも含まれている。ところがこの辛味成分は、すりおろすなどをして初めて生じる物質なのだ。もともと植物体の中では配糖体(シニグリン)として存在し、すりおろすなどして細胞を破壊し、酵素(ミロシナーゼ)反応が生じることで、揮発性のAITCが発生し、辛くなるのである。つまり、すりおろした状態で何もしなければ辛味がとんでしまい、ワサビ本来のよさが失われてしまうのである。だからといって、その都度根茎をすりおろさないというのは汎用性という側面からもかなり不利な要素であったはずである。
では、普及が困難に思えるワサビが、現代の日本に全国レベルで定着した背景には何があったのだろうか?
粉わさびの開発
多くの人が認めているように、私も「粉わさびの開発」が重要であったと考えている。粉ワサビを最初に開発したのは、小長谷与七である。与七は、静岡県の大富村で茶の仲買いをしていた経験から、製茶の製法から「ワサビも乾かして、粉にすればいつまでも保存することができさぞかし便利だろう」と考え、粉わさびの製造に乗り出したという。当初は、静岡県の川根方面のワサビを粉末にしていたが、これだけでは量産の見込みがないうえ価格も割に合わないため、ワサビの風味を損なわない程度にカラシ粉を配合したという。これによって量産が可能になり、事業が成功したとされている。
「調味料」として認められる
当時(昭和九(1934)年〜昭和十五(1940)年以降)ワサビは大量生産ができず、生ワサビだけでは粉わさびの原料をまかないきれていなかった。この事実が認識され、粉わさびは西洋わさびを原料とした「調味料」としての商品であることが、この機に公正取引委員会に正式に認められることになる。そこで、公正取引委員会は以下の規約を設けるに至った。
公正競争規約(昭和四十四年 公正取引委員会告示第三号)
「粉わさび」とは、西洋わさびを乾燥し、粉末化したものを主体とし、加工したものをいう。
このとき、わさびと誤認されるおそれがある文言、絵等の表示を禁止する事項等も記載されたことから、現在は原材料の西洋わさび(ホースラディッシュ)とわさびはわかりやすく区別され、表記されている。
当時、刺身はトレー包装され、冷蔵ショーケースのなかに並べられていたという。これに粉わさびを練ったものを添付しておくと、見た目も悪く、食卓にあがるまでに風味と辛味が抜けてしまうことがあった。そのためこの頃から「練りわさび」の開発が業界全体に望まれるようになる。その結果、1972年にはエスビー食品が、1973年には金印商品が、1974年にはハウス食品が相次いで「ねりわさび」を発売するようになった。これにより、ワサビはいっそう身近な存在になり、広く日本の食文化として浸透し、定着するようになったのである。ワサビがここまで普及するに至った背景には、民間企業によるたゆまぬ努力が存在していたことを忘れてはならないだろう。
ワサビのことをもっと知りたいならこの本!
『わさびの日本史』
・日本の魚食文化とワサビの相性
・「葵」の文字が入っているから? 徳川家康とワサビの意外な接点
・DNA分析で追う、植物としてのワサビの歴史とこれから
などなど、長年の研究を元にしたワサビのお話が満載!
Amazon
ヨドバシカメラ
honto

Author Profile
山根 京子
岐阜大学応用科学部准教授。専攻は栽培植物起源学。日本のワサビが中国大陸の類似種とは別種であることを示した論文で注目を集めた。ワサビ属植物の系統保存も行う。「全国わさび品評会」審査員。