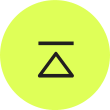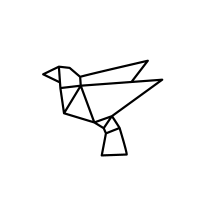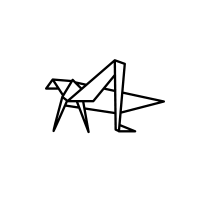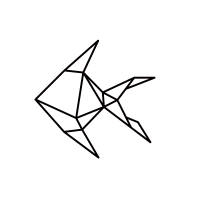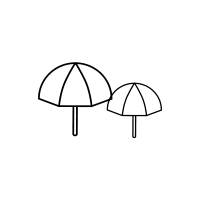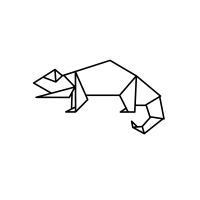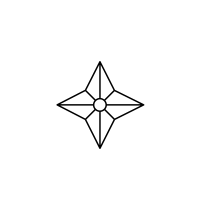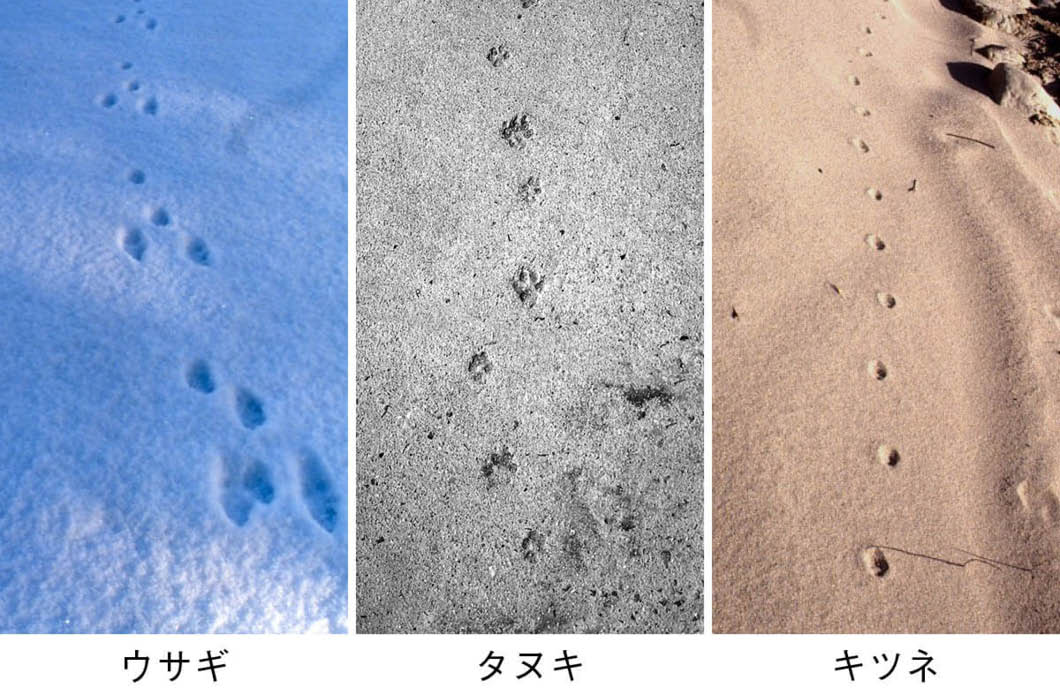【前編】ただの図鑑とは言わせない!! フリーターになってまで作った『ハエトリグモハンドブック』のハンパないこだわり
2017年6月、足かけ5年の制作期間を費やした『ハエトリグモハンドブック』がついに出版された。日本から確かな記録のある105種のうち103種を掲載し、私のハエトリグモへの愛をこれでもかと注ぎ込んだ、入魂の一冊である。今回、制作の舞台裏について書く機会をいただいたので、その狂気と称されるほどのこだわりを紹介したい。(筆者:須黒 達巳)

このクモ、誰でも一度は見たことがあるのではないだろうか。アダンソンハエトリというハエトリグモで、家の中にも現れる種
まず、本書のコンセプトは「野外で生きているハエトリグモを相手に、種名をつきとめる図鑑」である。
そのために、「可能な限り日本産の全種を」「生きた状態の写真で」載せることにした。しかし、生きているということは、動き回るということだ。つまり、それだけ撮影には手間がかかる。ならば、標本を写真に撮るのではだめなのだろうか? だめなのだ。
クモは標本を作るとき、瓶の中にアルコール漬けにする。クモは昆虫よりも体がやわらかいため、乾燥させるとボロボロになってしまうからだ。しかし、アルコールに漬けると、だんだんと体色は褪せていき、また姿勢も独特の「標本姿勢」になり、一般の人から見ると、生きているときの姿とはだいぶかけ離れたものになってしまう。だから「生きている」という条件ははずせない。
生きているのみならず、私は「その種らしく、かっこいい姿勢で」ということにもこだわった。これは、特徴をつかみやすいなどの機能的な面ではなく、完全に個人的な趣味である。ハエトリグモがどんな姿勢だろうと普通の人は気にならないと思うが、例えば我が子の七五三のときには少しでもかわいく、かっこよく撮ろうとするのと同じことだ。
ハエトリグモの良い姿勢とは、脚は広げすぎず縮みすぎず、腹は下がらず、できれば目線は少し上向き、といったところだ。クモの姿勢だなんてと思われるかもしれないが、これで生き生きして見えるかどうかがまったく違う。
じつは、生きた虫の写真を撮る際、「麻酔」をかける手段が存在する。二酸化炭素のスプレーをかけたり、冷蔵庫で体を冷やすと、動きを鈍らせることができるのだ。しかし、ハエトリグモの場合は、麻酔をかけるとその場にへたりこみ、明らかに元気のない「麻酔をかけました」という姿になってしまう。
せっかく図鑑に載るのに、覇気のない腑抜けたポーズではハエトリグモも浮かばれまい。というわけで、麻酔は一切使わず、すべて「生きて動き回っているものを」撮影した。

二酸化炭素スプレーで麻酔をかけたところ。脚に力がなく、腹も落ちていて格好悪い

カラスハエトリのオス。どっしり構えてくれることが多い、撮影者に優しい種

アリグモのメス。本物のアリもさることながらアリグモも止まることなく歩き続ける
ハエトリグモは種によって個性があり、白いプラ板の上に置くと(写真の背景を白くするため)、まずはじっと構えるタイプや、とにかく落ち着かないタイプ、カメラが気になって仕方ないタイプなどがいる。
カラスハエトリという種のようにすぐに落ち着いてくれるものならほんの1分ほどで撮影ができるが、アリグモの仲間はとにかく止まらない。そうなっては、カメラのオートフォーカスなど使い物にならないので、ピントは自分が前後に動いて合わせるしかない。撮影はとても集中力を要するので、あまりにも動き回られると「いい加減にしろ!!」と、忍耐の限界を迎える。カメラが気になるタイプというのは、おそらくレンズに映った自分の姿を別の個体と勘違いしているのだと思う。
やたらとレンズに飛びかかってきたり、カメラ目線のカットばかりが量産されたりする。これも、撮影を始めた頃なら愛くるしいしぐさに感じられたのかもしれないが、毎度やられると「それはもういい……」となる。

レンズに飛びかかってきたところ。奇跡のショットと思いきや、これが量産されることも
さて、我が子の七五三の場合、姿勢や顔つき以前に「衣装」にこだわるだろう。一生残る写真を撮るときに、しょうゆの染みがついたヨレヨレのシャツは着せまい。『ハエトリグモハンドブック』も同じだ。
と言っても、クモに着せる小さな服を作って、ということではない。「できるだけきれいな個体を撮影する」ということだ。
じつは、ハエトリグモの体の模様はおおむね毛でできているのだが、野外で出会う個体はしばしばその毛が擦れて、部分的に模様が失われている。命がけの過酷な日々を送る野生生物なのだから仕方がない。死線をくぐったのか、脚が1、2本欠けている個体もしばしば見かける。それはそれで伝わるものがあるが、せっかくの図鑑という晴れ舞台なので、きれいで魅力的に見える個体を載せたい。
一番きれいなのは、飼育下で脱皮をさせた個体だ。クモは脱皮をして大きくなるのだが、最後の脱皮をすると生殖能力をもった親になる。種を見分ける特徴は、親にならないとはっきりしないため、図鑑には載せるのは親である。であれば、わざと子どもを採ってきて、餌となるショウジョウバエやトビムシを与えながら飼って親まで育てれば、「野外で出会うよりも擦れや汚れのない、きれいな親」が得られるわけだ。
中には子どもから育て上げるのが難しく、親を採集して撮影せざるを得ない種もいるが、その場合でも「体型の調整」をする。クモは腹が柔らかく、空腹ならしぼみ、食べれば膨らむ。さらに、メスは卵を産むために大きな腹をもつため、「オスらしい体型」「メスらしい体型」というのがある。だから、痩せていたらエサをやって、元気そうな、その性らしい体型に調整するのだ。これは、どうしても餌付かなかった数種を除いてすべての種でやっている。
つまり、掲載したほぼすべての種を、少なくとも一時的には飼ったことがあるのである。

飼育の様子。一緒に入れると共食いするため、小さい容器に個別に飼う。多いときは容器が200個近く積んであった
飼うといっても、ある程度、育っている子どもを狙って採ってくるので、だいたいは1か月以内くらいで親になる。ただ、珍しい種になると、採集する個体の大きさを選んだりもできず、唯一採れたとても小さな子どもをがんばって育てなければならない、ということも起きる。
北海道のみに生息するタテジマハエトリは、じつに5か月かけて親まで育て上げた。八重山諸島に生息するツルギハエトリを育てたときは、順調に見えたがじつは体内に線虫が寄生していて、ある日、腹を破って線虫が出てきた。同じく八重山諸島に生息するムツボシハエトリは、水鉄砲のようにすばやく直線的に跳ぶことができるのだが、世話をする隙に容器から逃げ出し、ピュンピュン飛び回った挙句、なんと部屋の隅のゴキブリホイホイへと飛び込み、非業の死を遂げた。色々と苦労もあったが、すべてはその種の魅力を最大限に伝える写真を撮るためである。
最後に、巻末の「協力者」の中にある「須黒由紀」という人物について書いておこう。これは私の母である。
「そばで夢を応援してくれたという意味で名前を入れた」というような美しい話ではなく、私が採集旅行に出ている間、飼育しているクモたちの水やりを母に頼んでいたのだ。つまり、歴とした実務上の協力者なのである。自身も生き物や自然が好きで、世話を頼んでいる間も「マスラオというのが脱皮している」などと連絡をくれた。私を除いて、最も多くの日本産種を見ているのは、あるいは母かもしれない。
次回後編では、採集の舞台裏について紹介しようと思う。
【後編】ただの図鑑とは言わせない!! フリーターになってまで作った『ハエトリグモハンドブック』のハンパないこだわり

Author Profile
須黒 達巳
慶應義塾幼稚舎教諭.クモ,特にハエトリグモの研究に勤しむ.ウェブサイト「ハエトリひろば」を運営.主な著書に『ハエトリグモハンドブック』(文一総合出版),『世にも美しい瞳 ハエトリグモ』(ナツメ社).Twitter:@haetorihiroba