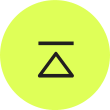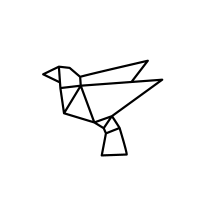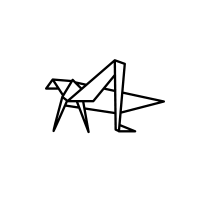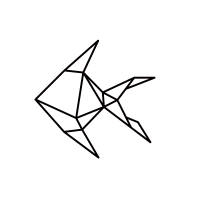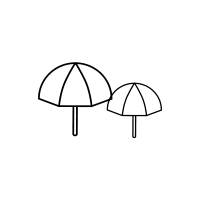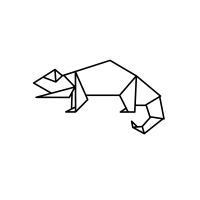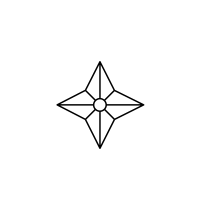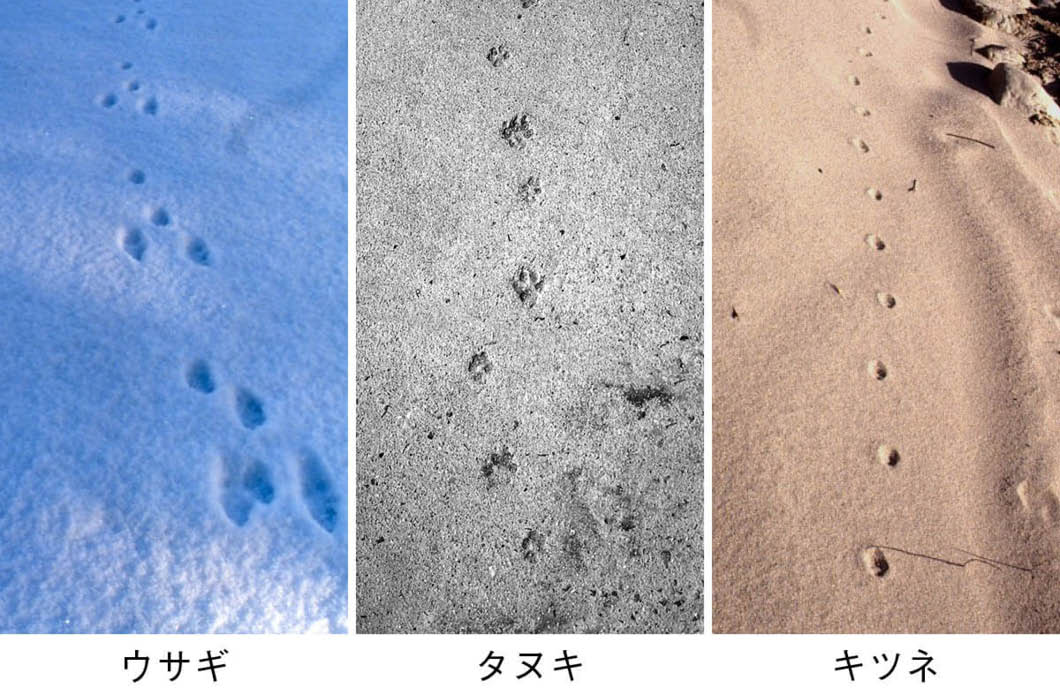小松貴が語る、洞窟に生きる虫たち
陸上にもかかわらず、まだまだ知られざる生物が潜む領域…それが「洞窟」。
その洞窟の中で人知れず生きる虫たちの特徴、そしてその奇妙でキテレツな魅力を、昆虫学者の小松貴さんが解説します。
(本記事は『陸の深海生物 日本の地下に住む生き物』から抜粋・編集したものです)
地下の暗闇に生きるものたち
地下世界といえば「洞窟」が真っ先に思い浮かぶ人も少なくはないだろう。古より、洞窟の内部にはおよそにわかには理解しがたいような風貌の生物が数多生息すること、そしてそれら生物種は大抵が特定地域の洞窟内でしか見られない様相を呈することが知られてきた。それゆえ、昔の研究者はこれらを「洞窟内に特異的に生息する生物」であるとみなしていた。

ホンドワラジムシ Hondoniscus kitakamiensis VANDEL
体長約3.0mm。眼がなく、全身が純白で美しいが、採集時に土砂で体が汚れてしまうことが多い。既存文献では「体表が平滑」とあるが、実際にはごく細かい顆粒状の突起が覆う。動きは鈍く、危険を感じると岩にしがみついて停止する。
岩手県岩泉町にある著名な石灰岩洞窟、龍泉洞で得られた個体に基づき、1968年に新種記載された。当時、湿った洞床の岩屑が堆積した場所で見つかったようである。しかしその後、同洞窟は大規模な観光整備が行われ、空気の流通の変化や照明の影響などで洞内環境が著しく悪化した。乾燥に弱い本種は洞内から姿を消し、その後存続の有無が長らく不明だったが、2019年に洞窟付近の地下浅層から複数個体が掘り出され、絶滅を免れていたことが発表された。後に盛岡市近郊の地下浅層からも見つかっている。
地下生活に究極に特化した「真洞窟性生物」
洞窟内に見られる生物は、そのスペックにより 3〜 4つのカテゴリに大別できる。 一つ目は、地下生活に究極に特化した、正真正銘の洞窟生物(真洞窟性生物)である。自発的に地上へ出てくることのないこうした生物たちは、分類群の垣根を越えておおむね共通した形態的特徴(眼が退化する、皮膚が薄くて体の色素が薄い、触角や脚が異様に細長い)をもつ。
暗黒の元で暮らすのに視力は不要なので、眼が退化するのは当然であろう。細胞を傷つける有害な紫外線にさらされることもないため、光線を吸収する皮膚の色素も必要ない。だから、洞窟の生き物には体が目の覚めるような純白だったり、真紅だったりするものがざらにいる。通常、そんな目立つ体色をしている生物など、すぐ捕食動物に見つかって食われてしまいそうなものだが、そこは地下世界。何しろ、光がまったく差し込まず、感光紙※1を数日間放置しておいても一切感光しないほどの環境だ。よって、視覚で獲物を探知する捕食動物が存在できない世界であるため、かような目立つ色彩の生き物が淘汰されずに生き残っていられるわけである。
皮膚が薄くて柔軟な体は、狭い地下の空隙をくぐり抜けるのには好都合だ。そして、暗黒下では視力の代わりに長い触角や脚を装備していたほうが、周囲の状況を感知したり起伏に富む深い縦穴の壁面を這い回るには役立つ。
地下性甲虫の場合、これらの特徴に加えて、地下性傾向がより強い種ほど体型がヒョウタンのようにくびれ、体高が盛り上がるという形態的適応※2(専門的にはアファエノプソイド aphaenopsoid と呼ばれる)が見られる。これは、腹部の背面にお椀状に変形した鞘翅がかぶさっているような状態であり、つまり腹部と鞘翅との間に空間ができているのだ。地下は湿度がとても高く、あらゆる物が結露する。こんなところに通常の形をした地上性甲虫がいようものなら、たちまち腹部と鞘翅の間に水がたまり、結果として腹部にある気門(昆虫が呼吸するための器官)が水でふさがって、陸にいながらおぼれてしまう。
無駄を極力削り、必要最小限のものだけを究極に研ぎ澄ませた生物の極致、それが彼ら、真洞窟性生物である。

キバナガメクラチビゴミムシ Allotrechiama mandibularis S. UÉNO
体長4.0-4.6mm。国内に400種以上知られるチビゴミムシ類の中でも、後述のアシナガメクラ(p.35)と並び地下生活に極度に特殊化した珍種。球磨川沿いに2か所ある、地下十数m以深もある縦穴の最深部でしか見つかっていない。
外見は、タカサワメクラをアファエノプソイド化(脚や触角の伸長、胴体がヒョウタン形にくびれる等の形態適応)したイメージ。細身の体はくびれ、脚や触角はクモのように細長い。そして、頭部と大顎は前方に長く突き出た奇観を呈する。動きは極めて素早く、漆黒の地底の岩盤上を風のように疾走する。
産地の洞窟はいずれも物理的に侵入困難だったり、個人での生物調査が不可能な管理洞窟であるため、顕著で有名な種にも関わらず、これまでこの虫の生きた姿を見る幸運に恵まれた者は史上10人にも満たない。上の個体は、大変な労力の末に特別な許可を得て洞窟調査を行い、わずか2日間の調査期間中、奇跡的に生け捕りに成功した唯一の個体。アシナガメクラと見比べてしまうと大して変わった種には見えないが、端正さ、得難さ、勇猛さ、どれをとっても日本最強。まさに究極のメクラチビゴミムシであると、ここに断言する。

サーベルのように鋭く突き出た牙。恐らく、活発に走りながらトビムシなど生きた小動物を捕食する。まさに生命を刈り取る、死神の鎌。

大概のメクラチビゴミムシは、歩行中に指で顔をつつくと進行方向を任意に変えられる。しかし、こいつにはそれが通用しない。一度向いた方向には是が非でも直進する。行く手を遮られると、むしろ激しく怒り出す。
好んで洞窟内で暮らす「好洞窟性生物」
二つ目は、洞窟内に好んで生息しているものの、絶対に洞窟内に生息することが生存の必須条件という訳ではない生物(好洞窟性生物)である。例えば、多くのカマドウマ類、リュウガヤスデと呼ばれるヤスデ類の場合、明らかに洞窟内に依存した生息の様相を呈しているが、これらは洞窟の外でも姿を見かける。
また、眼が退化したり極端に体の色素を失っているといった、典型的な真洞窟性生物にありがちな形態的特徴もあまりもたない。洞窟内と同程度に地上をも出歩く生活をしているため、視力や紫外線に対する耐性を完全に失う訳にはいかないのだろう。
洞窟と外界を行き来する「周期性洞穴性生物」
これと似ているようで違うのが、コウモリである。コウモリが洞窟に生息しているなどということは、誰でも知っている事実である。しかし、コウモリは夜になると洞窟を飛び出し、外で餌を捕る。つまり、洞窟は休んだり子を産み育てるのに使う拠点ではあるものの、食事は外に出て行わねばならないのだ。だから、(冬眠時期は除いて)コウモリは毎日夜間になると、必ず洞外へ出て活動し、翌朝までには再び洞に戻る。このように周期的に洞窟と外界を往復するタイプの生物を周期性洞穴性生物と呼ぶ。
たまたま洞窟へ紛れ込んできた「迷洞窟性生物」
最後が、たまたま地上から地下に紛れ込んできたような生物(迷洞窟性生物)。これはあくまでも偶然洞窟に迷い込んできたようなもののため、じきに再び地上へ戻るか、さもなくば暗黒下で生きていく術もないのでそのまま死ぬ。
福岡県にある石灰岩洞窟の牡鹿洞※3は、深さ30mあまりの垂直の縦穴となっており、穴の底では古い時代に滑落したシカやゾウ、カワウソといった動物たちの成れの果てである骨がたくさん見つかっている。こうした動物が、このカテゴリの範疇になるだろう。しかし、最近では真・好・迷の別なく「洞窟性」という言葉は、あまり意味をなさなくなりつつある。
なぜ、洞窟の虫にはまったのか?
人に話すとすぐその内容の信憑性を疑われるのだが、私は2歳の頃から、すでにメクラチビゴミムシという生物の存在を知っていた(ちなみに、アリの巣に居候して餌のおこぼれを盗み食いするアリヅカコオロギという、体長3mm程度のコオロギの存在も当時から知っていたし、実際に捕獲して遊んでいた。そして大学進学後、それの研究で博士号までとった)。

クボタアリヅカコオロギ。アリの巣に侵入し、餌を横取りして生きている。アリが巣仲間認識に使う体表成分をはぎ取って自分にまとうため、アリから存在を怪しまれない。
当時、住んでいた借家からさほど遠くない距離のところに観光地化された洞窟があり、父親はたまに気が向くとそこへ私を連れて行った。その入り口でもらえるパンフレットには、この洞窟内に生息している生物の紹介文が記されていたのだが、その中にここに生息する種のメクラチビゴミムシの粗いスケッチ画(原記載論文から転載したであろうもの)が載っていたのである。
もっとも、誤植なのか当時そのイラストの脇には「◯◯メクラチビゴミムシ」ではなく「◯◯チビコムシ」と書いてあったため、私はそれをチビコムシという名前の生き物だと思っていたのだが。全体的にそのパンフレットの記述は誤字脱字だらけで、「コオモリ」だの「ネズミコウモリ」だのと、存在しない生物の和名も書いてあった。
名前はともかく、幼い私はそのスケッチを見てえらく感動した。この洞窟の中に、こんな全身ヘンな毛が生えて眼がない虫がいるのか! ぜひとも見つけてやらねばなるまいて、と。もちろん、たかが2歳児が洞窟の中で大きさ数mmのメクラチビゴミムシ改めチビコムシなど発見できるはずもなく、実際にその洞窟内でそれを発見できたのは大学生になってからのことだった。
長野の辺鄙な大学で13年ほど青春を棒に振った後、私は紆余曲折あって九州に異動した。九州には、中部を中心に大小さまざまな洞窟(主に石灰岩洞窟)が無数に点在している。そのそれぞれに、チビコムシをはじめ特有の地下性生物たちが息づいているのだ。何せチビコムシに関して言えば、九州での種多様性は総本山たる四国のそれに次ぐ勢いである。これは見に行かない手はない。
という訳で、私は週末ごとに九州の随所にある洞窟を巡るようになってしまった。幼少期のチビコムシ体験という下地があったのに加えて、私は大学で主に地中のアリの巣に共生する生物の研究をやっていた。地底の生き物へそのまま興味が移るのは、もはや必然であった。
洞窟巡りのみならず、山沢の源流をつめての「土木作業」によりチビコムシを掘り出す技術も独学で習得した。始めのうちは失敗することが多かったが、次第にどういう環境に目を付けて掘ればいいかがわかってきたおかげで、打率も上がってきた。一番の思い出は、福岡・博多近郊のとある山で、未知のチビコムシを発見してしまったこと。なんとなく沢の源流の石をどけた時に赤い甲虫を見つけ、もしやと思ってよく見たら目のない奴だった。
その後その場所の沢沿いの土手を掘り、もう数匹採ることができた。この山は古くから多くの昆虫学者が訪れ、調べ尽くしたと言われていた場所だった。しかも、私がそこでそれを見つけたのは、九州に移住してわずか3週間目のことである。歴戦の学者たちの目をかいくぐり、この虫は私に発見されるまでずっとこの場所で眠り続けていたのかと思うと、感慨深いものがある。
気になる続きは…こちら!
『陸の深海生物 日本の地下に住む生き物』
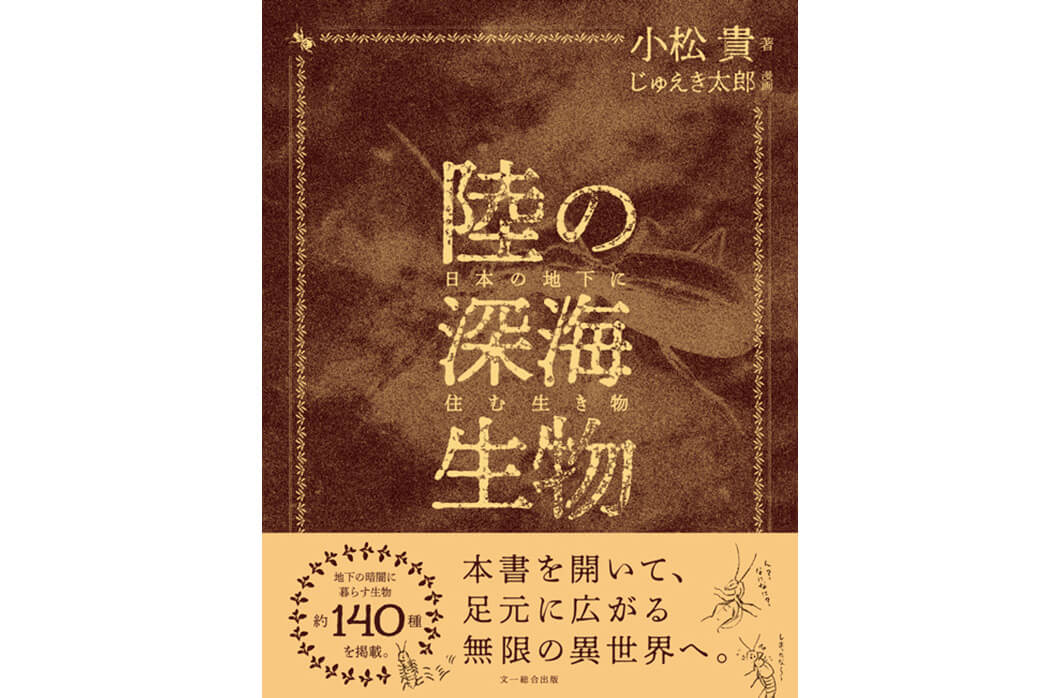

陸の深海生物と呼ばれる“地下性生物”約140種を収録。ふだん日の目を見ない彼らに情熱を注ぎ続ける昆虫学者の小松貴が、粉骨砕身して得た貴重な写真と共に、足もとの暗闇に広がる別世界へと読者を誘う。
2023年11月14日発売。
文一総合出版ホームページやお近くの書店、ネットショッピングでもお取り寄せできます!
紀伊國屋書店
honto
楽天ブックス
セブンネットショッピング
Amazon
Author Profile
小松 貴(こまつ たかし)
1982年生まれ。信州大学大学院博士課程を修了後、国立科学博物館協力研究員などを経て、現在在野の昆虫学者として活動。著書に『裏山の奇人』(東海大学出版部)、『昆虫学者はやめられない』(新潮社)など。