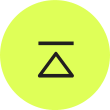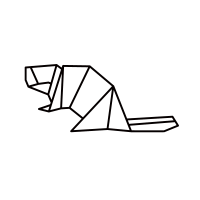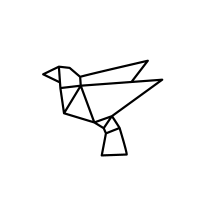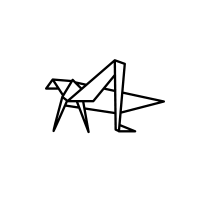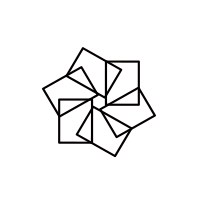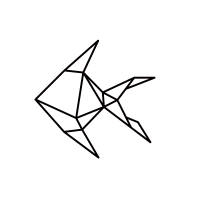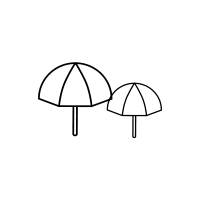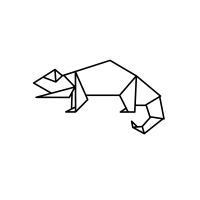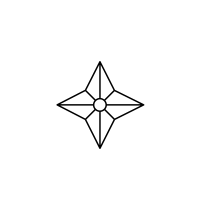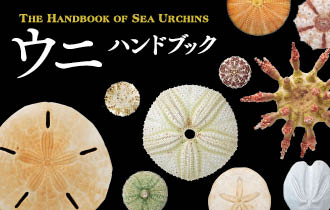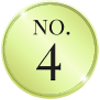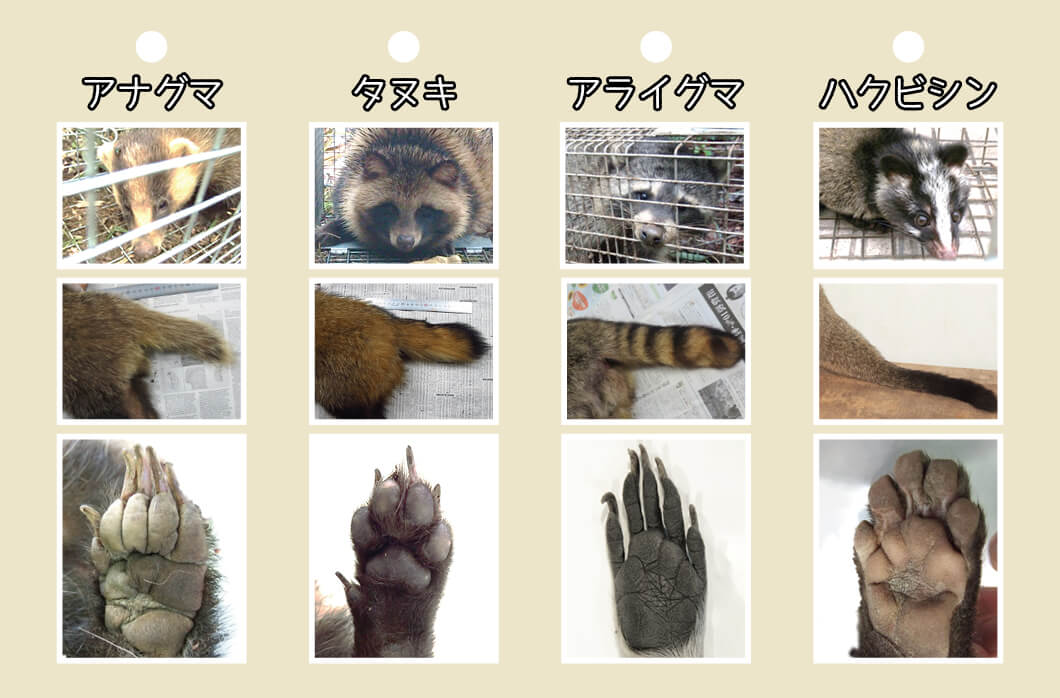大地を作る自然のパワー!
湿潤な気候に急峻な地形の日本列島。そんな土地柄の日本を歩いてみると、しばしば不思議な地形を目にします。それらは自然界が持つある種の力によって形作られています。
『日本列島 大地の成り立ち図鑑』では、そんな不思議な地形がどうやってできているのかを類型的に解説しています。今回はそんな本書から、火山の力によってできる「カルデラ」と、水の力によって独特の地形となった「穿入蛇行」について紹介します。
巨大噴火でできた国内最大級の阿蘇カルデラ
日本列島には多くの火山があります。その大規模な噴火活動で、マグマや火山灰を多量に放出すると地下が空っぽになり、地表がくずれて大きなくぼ地が生まれます。この鍋のようなくぼ地(直径2km以上)を カルデラ といいます。
国内にあるカルデラのなかでも、九州の阿蘇カルデラ(写真)は最大級の規模を誇ります。東西18km、南北25kmと大きく、約27万~9万年前にかけて4回の巨大噴火を起こしました。とくに、4回目の噴火では多量の火砕流火山灰を放出し、火砕流は160kmはなれた山口県まで、火山灰は1500kmはなれた北海道にまで届きました。このときの噴出量だけで富士山の全体積を超えるほどだったのです。
その後も、日本各地でカルデラができる破局噴火(カルデラ噴火)が起こりましたが、もっとも新しいカルデラ噴火は鬼界カルデラ(鹿児島県)で、約7300年前とされています。それ以降、カルデラ噴火は起こっていませんが、この先も起こらないとはいい切れません。


阿蘇の草千里火口。中央火口丘の西に位置し、約3万3000年前にデイサイト溶岩を噴出した。

阿蘇カルデラは九州の中心部となる熊本県東部に位置する。

阿蘇の米塚。約3000年前の噴火でできたスコリア丘で、火口から噴き出したスコリアが積み重なったもの。
四国最長の川がつくった穿入蛇行
穿入蛇行 とは、山地の川がくねくね曲がった谷をつくって流れることです。これは、土地が高くなること( 隆起 )によって、蛇行する川が谷を下方へ削ること( 下刻 )で発達します。土地が隆起すると、蛇行する川は谷底を削るだけではなく、カーブの外側も削るため蛇行は側方へ延びていきます。そのため、カーブの外側は急斜面となるのです。
日本の川は山地を流れる区間が多く、全国各地に穿入蛇行をつくっています。なかでも、穿入蛇行が激しい川は四国の四万十川です。この川は四国でもっとも長い196kmを流れますが、その大半が山地をくねくねと蛇行しています。この穿入蛇行がくり返される区間は、フィリピン海プレートの沈み込みによって起きる土地の隆起だけではなく、 白亜紀付加体 ※の砂岩や泥岩など比較的硬く、かつ硬さに変化が少ない岩盤を流れることも関係しています。
※恐竜が繁栄した白亜紀(約1億2500万~約6600万年前)に、海洋プレートの沈み込みによって、同プレート上の地層や岩石が大陸プレート側にくっついてできた地層。長い年月をかけて地上へ押し出され、日本列島の一部となりました。

四万十川が、白亜紀付加体の泥岩地帯を複雑に穿入蛇行する。下記地図上のa地点。

四万十川支流の黒尊川がつくるショートカット寸前の穿入蛇行。下記地図上のb地点。

四国の南西部をくねくねと流れる四万十川。
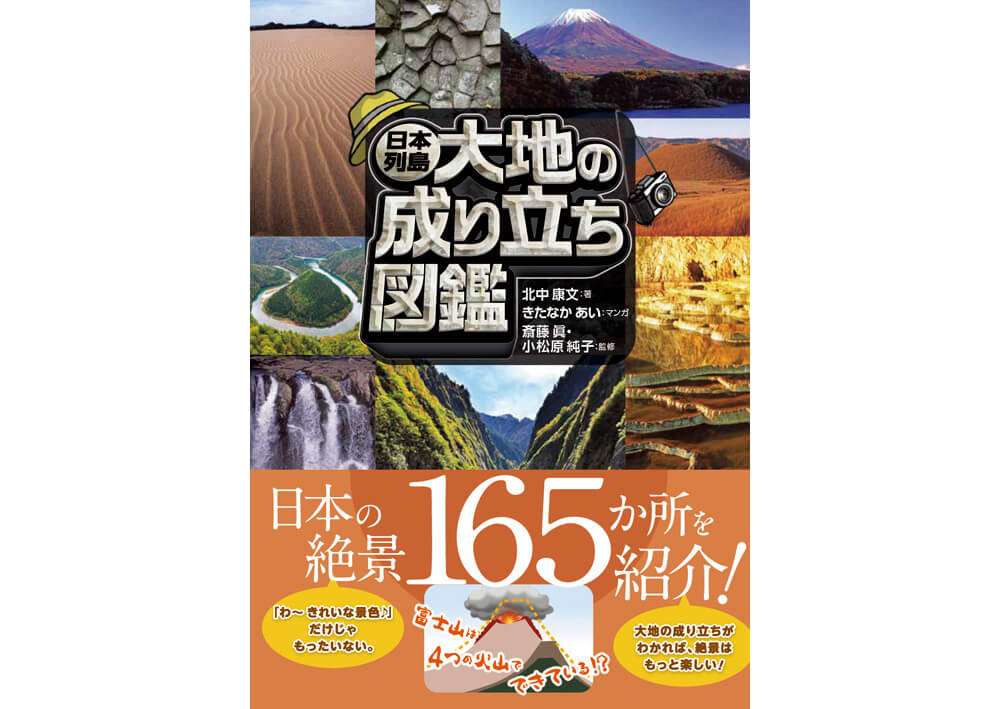
北中康文 著 / きたなか あい マンガ / 斎藤 眞・小松原純子 監修 / A5判 / 160ページ
ISBN 978-4-8299-9026-1 2025年6月20日発売
定価2,200円(本体2,000円+10%税)
日本の絶景と地形の成り立ちがわかる地学ガイド。カルデラや峡谷、流れ山といった地形がどのように形作られたのかを、マンガと写真でわかりやすく紹介。日本列島の歴史や火山活動、プレートの動きなどを学べる一冊。小学生から大人まで楽しめる図鑑です。
Amazon|楽天ブックス|ヨドバシ
Author Profile
北中 康文(きたなか やすふみ)
1956年、大阪府生まれ。自然写真家として全国の滝、川、地形地質などをテーマに幅広く活動。日本列島の魅力を写真で掘り下げる。信条は「写真は肉眼を超える」。主な著書に『日本の川』、『日本の地形・地質(共著)』、『日本の滝』、『風の回廊―那須連山』などがある。2007年「日本地質学会賞」受賞。